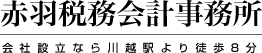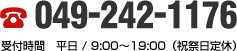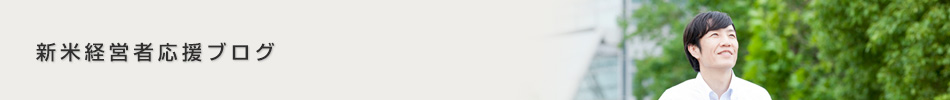合同会社は個人事業主と異なり、仕訳や決算など、税務に関する多くの作業があります。専門的な知識も必要となるため、顧問税理士をつけようかと考えている事業主もいるでしょう。
本記事は、合同会社は顧問税理士が必要なのかについて解説します。費用の相場や、税理士費用を安くする方法について紹介します。顧問税理士をつけるメリット・デメリット、および税理士選びのポイントについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
合同会社に顧問税理士は必要?
合同会社を設立し、事業運営するには、経理や税務関連において専門的な知識が必要です。そのため、顧問税理士が合同会社に必要です。
ここでは、合同会社に顧問税理士が必要な理由、および依頼のタイミングについて解説します。
設立から依頼すればスムーズで無駄のない手続きが可能
合同会社の設立時から税理士に依頼すれば、定款作成や各種届出書類の準備、税務署などへの手続きなどがスムーズに進みます。
設立後の経理事務や税務処理に関しても、無駄な手間が省け、安心して事業をスタートできるでしょう。
法人の経理業務や税務会計が複雑なため設立後も必要
合同会社の設立後は、帳簿の作成や給与計算、決算事務や消費税や法人税の申告など、専門的な業務が発生します。個人事業に比べ、法人は税務処理が煩雑で、遵守すべき法令も多岐にわたります。
顧問税理士をつけていれば、税務や財務のサポートが期待できるので安心です。節税や資金繰りのサポートが受けられることも期待できるでしょう。
合同会社が顧問税理士をつけるタイミング
合同会社が顧問税理士をつけるタイミングとして、「合同会社の設立を検討中・決めたとき」「合同会社の設立後に事業に集中したいと考えたとき」が考えられます。
合同会社の設立を検討中・決めたとき
合同会社の設立を検討中や設立を決めたときは、顧問税理士をつけるタイミングとして考えられます。法人設立には、定款の作成や、税務署や都道府県・市区町村への各種届出など、多くの書類の作成が必要です。税理士に依頼すれば、それらの準備をスムーズに進められ、設立後に書類不備でやり直すことも軽減されます。
合同会社の設立後に事業に集中したいと考えたとき
合同会社設立後、売上をあげることやサービス開発に集中したいと考えたときに、顧問税理士をつけるタイミングとして適しています。
日々の帳簿付けや請求書管理、源泉所得税の納付などは、時間と手間が必要です。
これらを税理士に任せることで、経営者は売上拡大や事業運営といった本来注力すべき業務に集中できます。
法人税・消費税などの申告はミスが許されません。経営者自らが行った場合、うっかりミスにより、誤った申告を行うとペナルティが課される恐れがあります。
顧問税理士がついていれば、期限管理や申告書の作成を正確に代行してもらえるため、安心して事業に専念できるでしょう。
合同会社が税理士に依頼する際の費用相場
合同会社が税理士に財務・会計業務を依頼する場合、どれくらいの費用が必要でしょうか。
合同会社を設立に必要な費用および顧問料の相場について紹介します。
合同会社設立費用
合同会社を設立した場合、主な費用として、以下のものがあります。
- 定款用収入印紙代
- 登録免許税
定款用収入印紙代は、紙の場合4万円、電子定款の場合は不要です。登録免許税は、6万円または資本金額の70%のいずれか高いほうです。設立費用として、6~10万円かかることになります。
税理士顧問料の相場
合同会社を設立し、税理士と顧問契約を結ぶ場合、顧問料が発生します。顧問料は、売上や業種、税理士に依頼する作業量により大きく異なります。通常、月額顧問料は1万円~5万円が相場です。また、年に1度の確定申告および決算申告に際しての費用相場は、15万円ほどとされています。
上記以外にも、年末調整や消費税申告について依頼する場合、別途費用が必要です。税理士と顧問契約を依頼する場合、何にどの程度費用が必要なのかを、見積書を発行してもらい、確認するようにしましょう。
合同会社が税理士費用を安く抑える方法
税理士に依頼すると必要な費用を紹介しましたが、合同会社の経営者によっては、もう少し費用を抑えられないかと考える人もいるかもしれません。
税理士費用を安く抑える方法として、以下の3点があるので、それぞれ紹介しましょう。
- 記帳を税理士に依頼しない
- 決算申告だけ依頼する
- クラウド会計ソフトの活用
記帳を税理士に依頼しない
記帳を税理士に依頼せずに、自社で記帳する方法は、税理士費用を抑えるのに有効です。税理士に記帳代行を依頼すると、取引件数や仕訳数に応じて報酬が上乗せされることが多く、コストがかさむ要因になります。特にスタートアップや小規模な合同会社の場合、日々の取引件数が限られているため、自社で記帳作業を行っても負担にならないでしょう。
決算申告だけ依頼する
税理士費用を抑えたい場合、顧問契約ではなく決算申告だけ、といったスポットで依頼する方法があります。日常の記帳業務は自社で行い、決算や法人税申告といった年1回の手続きのみを税理士に任せることで、コストを大幅に抑えることが可能です。
記帳の精度が求められるため、会計ソフトの活用や基本的な経理知識もあわせて必要になります。
クラウド会計ソフトの活用
クラウド会計ソフトを活用することも、税理士費用の削減に役立ちます。銀行やクレジットカードなどの取引データが自動で連携でき、手入力の手間が減り、効率のいい会計処理ができます。税理士側も、データをそのまま活用できるため、作業工数の削減が可能です。
特にクラウド会計に対応している税理士であれば、リアルタイムでデータ確認ができるため、スムーズな対応が見込めるでしょう。
合同会社が顧問税理士をつけるメリット
合同会社が顧問税理士をつけると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
主に以下の4点がメリットとして考えられるので、順を追って解説します。
- 正確な決算業務が行える
- 資金繰りや経営に関するアドバイスが得られる
- 節税対策の助言が受けられる
- 税務調査の対応も代行してもらえる
正確な決算業務が行える
顧問税理士をつけることで、正確な決算業務が可能です。納税申告においても、間違うことがほぼなく、税務署からの修正申告や追徴課税なども受けません。
また、対外的に会社の信頼性がアップすることが見込まれます。例えば金融機関に融資を申し込む場合、顧問税理士が作成した決算書類であれば、間違いないものと見做され、融資審査においても好印象が持たれます。
資金繰りや経営に関するアドバイスが得られる
資金繰りや経営に関するアドバイスを顧問税理士より得られることも、、合同会社が顧問税理士をつけるメリットです。
顧問税理士は、自社のキャッシュフローを認識しているため、適切な助言が見込まれます。自社の資金が不足するタイミングも把握しているため、タイムリーな金融機関の借入について提案できます。
自社が利用できる補助金・助成金に関してのアドバイスが期待できるので、資金繰りの安定や改善が見込めるでしょう。
節税対策の助言が受けられる
節税対策の助言が受けられる点も、顧問税理士がついているメリットです。顧問税理士がいない場合、仮に経営者が誤った節税を行うと、違法な節税対策となります。追徴課税を支払うだけでなく、自社の信用失墜につながりかねません。
顧問税理士がいると、適切な助言が受けられ、正しい節税が可能となります。
税務調査の対応も代行してもらえる
顧問税理士がついていれば、税務調査の代行も可能です。法人が事業運営を行っていると、税務調査は不可避です。顧問税理士がいなければ、税務調査が入った場合、自社で対応しなければなりません。適切な対応ができなければ、税務調査官より疑いの目で見られる恐れがあります。
顧問税理士がいれば、自社に代わって対応してくれるので、税務調査官とも円滑なやりとりが見込まれます。
合同会社が顧問税理士をつけるデメリット
一方で、合同会社が顧問税理士をつけるデメリットとして、次の3点があるので紹介します。
- 費用がかかる
- すべての情報開示が必要
- すべて丸投げできないこともある
費用がかかる
顧問税理士をつける最大のデメリットは、毎月の顧問料や決算申告時の報酬など一定の費用がかかることです。小規模な合同会社にとっては、重い経費負担となるかもしれません。
税理士によって報酬体系も異なるため、依頼前にサービス内容と費用のバランスをしっかり確認しておくことが大切です。
すべての情報開示が必要
顧問税理士をつける以上、正確な申告や節税対策を任せるには、知られたくない情報等があっても、会社の財務状況や取引内容をすべて開示する必要があります。
しかしながら、税理士には守秘義務があるため、業務で知り得た情報を第三者に漏らすことはありません。そのため、安心して情報開示することが可能であり、おすすめです。
すべて丸投げできないこともある
顧問税理士に依頼すれば多くの税務業務を任せられますが、すべてを丸投げできるわけではありません。
領収書や請求書の整理、日々の取引の記録など、自社が対応すべき業務もあります。
対応すべき業務を疎かにすると、税理士との連携が取れなくなる恐れがあります。正確な申告や帳簿作成に支障をきたすことが考えられるので、注意が必要です。
税理士を選ぶポイント
合同会社が顧問税理士を選ぶ場合、以下の点に注意することが必要です。
- 事務所次第では丸投げできない
- 業界・業種の知識がある
- 気軽に相談できて相性が合う
それぞれ、順を追って解説します。
事務所次第では丸投げできない
税理士事務所によっては対応範囲が異なり、記帳代行サービスを行っていない税理士事務所もあるので注意が必要です。
記帳代行サービスを行っていない税理士事務所と顧問契約を結ぶと、自社で経理担当者を雇わなければなりません。
税理士と顧問契約を結ぶ場合、税理士事務所の対応可能範囲を十分確認しましょう。
業界・業種の知識がある
自社の業界や業種に詳しいかどうかも、税理士を選ぶポイントのひとつです。業種ごとに税務処理や必要な届出書類、節税のポイントが異なります。知識がある税理士であれば、実務に即したアドバイスを受けられます。
例えば、ITや建設、医療など独特の会計処理がある業界では、経験豊富な税理士を選ぶと安心でしょう。
気軽に相談できて相性が合う
顧問税理士を選ぶ場合、気軽に相談でき、相性の合う税理士を選ぶことが大切です。
顧問税理士とは継続的な関係を築く必要があるためです。
専門知識が豊富であっても、相談しづらい税理士であれば、知りたいことも聞けなくなる恐れがあり、ストレスがかかります。
気軽に質問できる雰囲気や、コミュニケーションが密に取れる税理士を選ぶようにしましょう。自社の意図を汲み取ってくれる税理士を選ぶことで、パートナーとして長期的に信頼関係が築けます。
まとめ
合同会社は、顧問税理士が必要です。個人事業主と異なり、決算や申告や確定申告等、専門的な知識が必要だからです。
税理士と顧問契約を結ぶ場合、顧問料が発生し、月額1~5万円が相場とされています。税理士費用を安く抑える方法として、記帳を税理士に依頼しなかったり、決算申告だけ依頼したりするなどの方法があります。
合同会社が顧問契約をつけるメリットは、正確な決算業務が行える、資金繰りや経営に関する助言がもらえるなどの点です。一方で、費用がかかる、すべての情報を開示するなどといったデメリットもあります。
自社の業界や業種について精通している、相性が合うなどが税理士を選ぶポイントです。
本記事が、自社に適した税理士を選ぶ参考になれば幸いです。