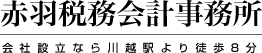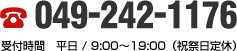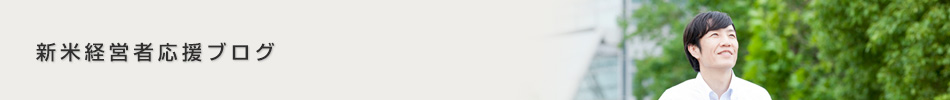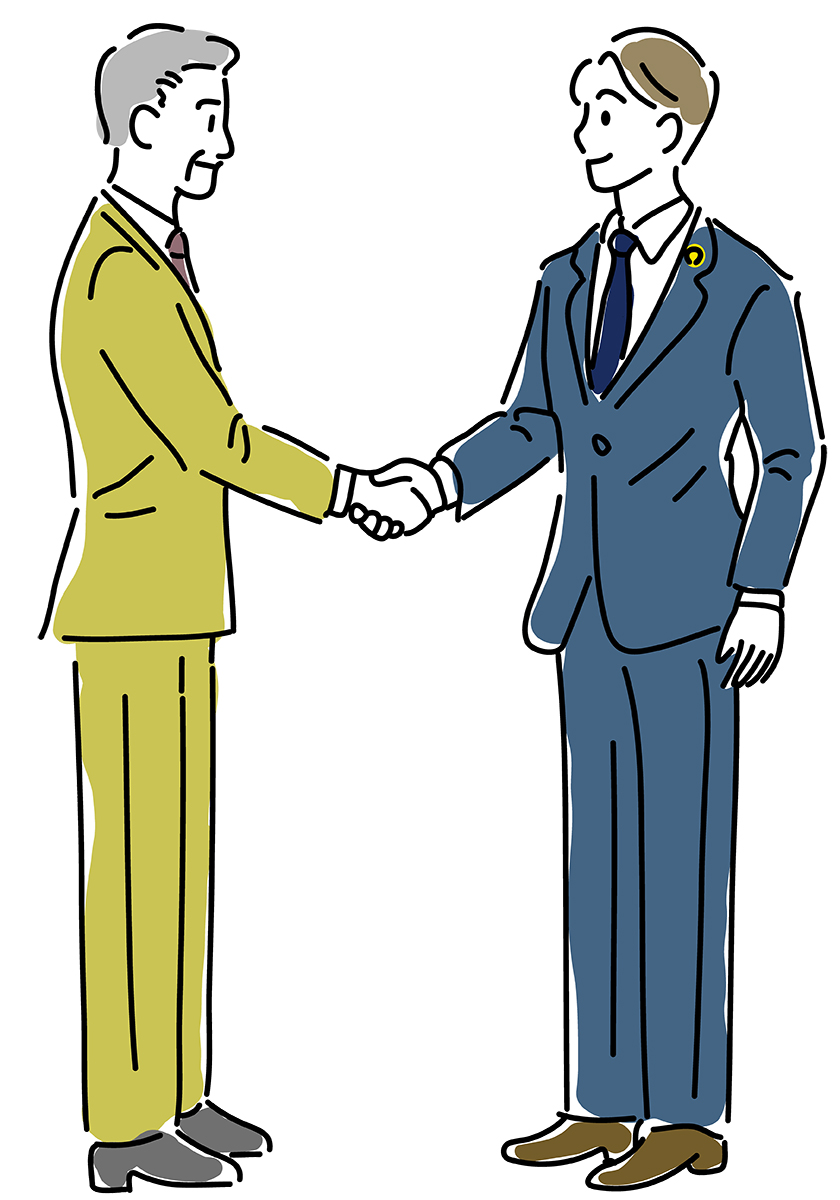
個人事業主の中には、会社を設立し、事業の拡大を目指している事業者もいるかもしれません。その前に、法人化を検討するにあたって、どのようなメリットやデメリットがあるのかを認識しておく必要があります。
本記事では、会社設立のメリットとデメリットについて解説します。
どのような個人事業主が会社設立に適しているのか、会社設立の流れおよび費用について紹介しますので、会社設立を検討している個人事業主の方はぜひ参考にしてください。
会社設立のメリット
会社を設立するにあたってのメリットとしてどのような点があるのかについて解説します。
主なメリットとして、次の7点あるので、順を追って紹介しましょう。
- 税金面で有利になる
- 経費計上できる範囲が広い
- 欠損金を10年間にわたり翌年度以降へ繰り越せる
- 消費税の納付を最大2年間免除できる
- 決算のタイミングを自由に決定できる
- 取引先や金融機関など社会的な信用が高まる
- 資金調達がしやすくなる
税金面で有利になる
個人事業主が支払う所得税は累進課税で、税率は5%~45%まであります。所得が増えるほど税率が上がる仕組みです。
一方法人が支払う法人税は、所得800万円以下は約15%、それ以上は23.2%です。
個人事業主の事業所得が900万円以上になる場合、法人化すると税負担が軽くなります。そのため、個人事業主の課税所得金額が増えるほど、法人税の方が有利になり、結果として手元に残る資金が増えていきます。
経費計上できる範囲が広い
法人化することで、経費として認められる範囲が個人事業主よりも拡大する点も会社設立のメリットといえます。役員報酬や従業員への給与・賞与はもちろん、家族従業員への支払いも要件を満たせば経費可能です。
また、社宅や水道光熱費・通信費といったオフィス関連の費用も、法人ならより広い範囲で経費計上でき、節税効果が高まります。
欠損金を10年間にわたり翌年度以降へ繰り越せる
会社設立の場合、青色申告を行っていれば赤字(欠損金)を最長10年間繰り越して、将来の黒字と相殺できるメリットがあります。個人事業主の場合では赤字を繰り越せるのは最大3年であることに比べ大幅に長く、事業立ち上げ期の赤字も将来に活かせる点が強みです。
黒字化した年に累積赤字分が控除され、税負担が軽減されます。会社設立することで、長期的な税務戦略を立てやすくなるのも魅力といえるでしょう。
決算のタイミングを自由に選択できる
法人では決算期(月)を自由に選択できる点もメリットのひとつです。繁忙期を避けることで業務のピークを分散でき、会計・経理における負担の軽減が可能です。また、決算月を戦略的に選ぶことで、節税やキャッシュフローの改善にもつながる可能性があります。
個人事業主に比べ、年度の区切りを自社で決められる点は、経営計画の立てやすさという意味で大きな利点といえます。
取引先や金融機関などから信用力が高まる
法人は登記によって名称・代表者・資本金などが公開され、透明性と信頼性が向上します。
そのため、取引先や金融機関からの信用力が高まり、高額取引や契約の締結にもつながりやすくなります。
個人事業主であれば取引を断られるケースでも、法人であることにより、取引が可能となる場合もあり、営業機会の拡大にも有利に働くでしょう。
資金調達が受けやすくなる
法人は出資による資金調達が可能なほか、金融機関からも信用を得やすいため、融資を受けやすく点もメリットです。
株式会社であれば、株式発行によってベンチャーキャピタルやエンジェル投資家等の投資を募ることも容易になり、返済不要の資金調達手段も得られます。
融資においても、個人事業主より透明性ある会計処理がされていると考えられるのが一般的であるため、個人事業主と比較し審査も通りやすい傾向にあります。
会社設立のデメリット
会社設立はメリットばかりではありません。一方で、デメリットも存在する点にも注意しましょう。主なデメリットは以下の4点です。
- 費用と時間がかかる
- 赤字の場合でも法人住民税を支払わなければならない
- 社会保険に加入する必要がある
- 事務の負担が増える
費用と時間がかかる
会社設立には、定款認証費用や登録免許税などの初期費用が必要です。さらに、登記書類の作成や法務局への申請などの手続きが必要で、準備から設立完了まで数週間かかることもあります。
専門家に依頼すれば手間は省けますが、その分コストも発生します。個人事業の開業届に比べ、費用・時間の両面で負担が大きくなる点は理解しておくことが必要です。
赤字の場合でも法人住民税を支払わなければならない
法人は利益の有無にかかわらず、毎年最低7万円(自治体によって異なる)の法人住民税が課税されます。これは赤字であっても免除されないため、売上が不安定な初期段階では負担感が大きくなるかもしれません。
個人事業主であれば所得がゼロなら住民税は発生しませんが、法人では固定費として必ず計上する必要があります。会社設立前に損益計画を慎重に立て、最低限の税負担に耐えられるかどうかもチェックしましょう。
社会保険に加入する必要がある
すべての法人は役員1人だけの会社であっても、法律により健康保険と厚生年金保険に加入する義務があります。
健康保険と厚生年金保険の保険料は、会社および被保険者で50%ずつ負担しなければなりません。社会保険は将来の年金受給額や保障面でメリットがありますが、短期的には経費負担が増加します。
個人事業主が国民健康保険・国民年金に加入している場合と比べると、特に設立初期には負担増を実感しやすい項目といえるでしょう。
事務の負担が増える
法人化すると、毎月の経理処理や年1回の決算、税務申告に加え、社会保険・労働保険関連の届出など事務作業が増えます。帳簿の記帳方法も複雑になり、法人税申告書や決算書など専門的な書類作成が必要です。
これらは自社で行うことも可能ですが、税理士や社労士への依頼を検討するケースが多く、その場合は報酬コストも発生します。
事務負担の増加は、時間的・金銭的な負担がかかる点を認識しておくことが必要です。
どのような個人事業主が法人設立を検討すべきか
法人設立のメリット・デメリットについて解説しましたが、実際にどのような個人事業主が会社設立に適しているのでしょうか。
以下では、会社設立を検討するのに適したケースについて紹介します。
年間の事業所得が目安として1,000万円前後ある
個人事業主の場合、課税所得金額が1,000万円を超えると、所得税の累進課税による税負担が大きくなります。900万円以上の課税所得金額の場合、税率が33%となります。
法人化すれば、法人税率は最大でも23.2%です。特に、課税所得金額が900万円から1,000万円ほどになる場合には、法人化した方が税負担を抑えられることが期待できます。
資金調達の幅を広げたい
法人は、金融機関からの融資を受けやすくなるほか、株式会社であれば株式発行による出資を募ることも可能です。出資の場合、返済不要の資金調達が可能です。
個人事業主では限られる資金調達手段も、会社設立により多様化し、成長スピードを加速できます。将来的な事業拡大を見据える場合、法人化は資金戦略の幅を広げる有効な手段といえるでしょう。
家族に給与を払い経費にしたいとき
会社を設立すれば、家族を役員や従業員として雇用し、給与を支払うことでその金額を経費として計上可能です。
個人事業主の場合、一定の要件を満たさなければ家族に給与を支払っても経費として認められないケースがあります。
法人なら、青色専従者給与の申請が受理されれば、家族に支払った給与も経費として扱え、家族への所得分散が実現し節税効果が見込めます。
従業員を雇い入れたいと考えたとき
従業員を雇用する場合、法人化することで、雇用契約や社会保険制度の整備がしやすくなり、求職者からの信頼も高くなります。福利厚生や給与体系を明確に提示できることで、優秀な人材の採用に有利に働くでしょう。
法人化により組織としての体制が整うことで、従業員の定着率向上や業務の効率化も期待できます。今後の事業拡大を目指すにあたって法人化することは、人材確保の大きな役割を果たすでしょう
。
会社を設立する際の手続きおよび費用
会社設立は、個人事業主のように所轄の税務署へ開業届を提出すれば完了する簡易な手続きではありません。
ここでは、会社を設立する際に必要となる手続きの流れや、それに伴う費用について解説します。
会社設立の手続きの流れ
以下では、会社を設立するまでの流れは以下の通りです。
①会社設立事項の決定
②提出書類の作成
③定款の作成および認証
④出資金を払う
⑤登記申請書類の作成・登記申請
①会社設立事項の決定
会社設立の際、商号(会社名)や本店所在地、事業目的・資本金・発行株式数および役員構成などの基本事項を決定しなければなりません。
これらは定款や登記申請に記載される重要情報であり、後から変更するには追加費用や手続きが必要なので慎重な検討が求められます。
②提出書類の作成
会社設立には、法務局や公証役場に提出する書類が複数必要です。主な書類は定款、登記申請書、役員の就任承諾書、印鑑証明書および資本金の払込証明書などです。
書類の不備は手続きの遅れや再提出の原因となるため、正確さが求められます。専門家に依頼すれば効率化が見込めますが、その分報酬が発生します。
自分で行う場合は、各役所や法務局の最新書式を確認しながら進めましょう。
③定款の作成および認証
定款は会社の基本ルールを定める重要書類で、商号や目的・所在地・資本金・発行可能株式総数などを記載します。
株式会社の場合は、公証役場での認証が必要で、認証手数料と印紙税(電子定款の場合は不要)がかかります。定款は将来の経営判断や組織変更にも影響するため、専門家のアドバイスを受けながら作成するのが望ましいです。
④出資金を払う
定款認証後、発起人が出資金を会社名義の口座に払い込みます。設立前は会社口座が開設できないため、代表者の個人口座を利用するのが一般的です。
払込が完了したら、その通帳のコピーをもとに「払込証明書」を作成します。この払込証明書は登記申請時に必要な書類であり、金額や日付が明確に確認できる形で提出する必要があります。
⑤登記申請書類の作成・登記申請
法務局への登記申請は、会社設立日を確定させる重要な手続きです。申請書には会社の基本事項や役員情報、資本金額などを記載し、定款や払込証明書、役員就任承諾書など必要書類を添付します。
登記が完了すると、会社の法人格が正式に発生し、登記事項証明書や法人印鑑証明書が取得可能となります。
会社設立にかかる費用
会社設立には、主に以下の費用が必要です。ここでは株式会社を例に取り上げます。
【株式会社設立費用】
| 内容 | 費用 |
| 定款に貼付する印紙代 | 4万円(電子定款なら印紙税は不要) |
| 定款認証手数料 | 5万円 |
| 株式払込事務取扱手数料 | 払込資本金×約0.25% |
| 登録免許税 | 払込資本金×約0.7% |
その他、司法書士などに依頼する場合、別途費用がかかります。
まとめ
会社設立は、節税や信用力向上など多くのメリットがある一方、費用負担や事務作業の増加といったデメリットも存在します。
個人事業主は、自身の事業規模や将来の成長計画に照らして判断することが重要です。
個人事業主が現状を把握し、同時に本記事で紹介したポイントを踏まえ、会社設立によって得られる効果と負担を比較検討することが重要だといえるでしょう。