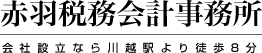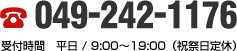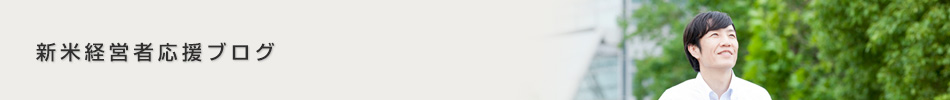企業経営において、会計監査は単なる義務にとどまらず、財務情報の信頼性を確保し、対外的な信用を高める重要な役割を担います。特に上場企業や一定規模以上の会社にとっては、法的に監査が義務付けられており、期末の決算時期を中心に実施されるのが一般的です。
本記事では、会計監査の基本的な目的や法的な位置づけ、種類の違いについて解説します。
実際の監査の流れや確認される内容、さらには会計監査を受ける際に注意すべきポイントについても紹介します。
会計監査とは
会計監査とは、企業が作成した財務諸表が正確かつ適正に作成されているかを監査人がチェックする仕組みです。
主に公認会計士や監査法人が担当し、企業の財務情報が外部利害関係者にとって信頼できるものであるかを確認します。
ここでは、会計監査の目的や実施の時期、対象となる企業について解説します。
会計監査の目的
会計監査の目的は、企業の財務諸表が適正に作成されているかを外部に証明するためのもので、投資家や取引先、金融機関など利害関係者(ステークホルダー)も閲覧可能です。
正確な財務情報をもとに意思決定できるよう、会計監査は企業の信頼性を担保する役割を果たします。また、企業内部の不正会計やミスを防ぐ抑止力としても機能します。
会計監査の法的義務が発生する対象企業
会計監査はすべての企業に義務づけられているわけではありません。
会社法により一定の要件を満たす「大会社」や、金融商品取引法の規定に基づく上場企業などに対して義務が発生します。
他にも、国や地方自治体より補助金を受けている学校法人や、独立行政法人なども会計監査の対象となっています。
法令で会計監査を受ける義務があるにもかかわらず実施しなかった場合、罰則が課されたり上場廃止になったりすることがあるので、上記に該当する法人は受けなければなりません。
会計監査を実施する時期
会計監査は、企業の決算期に合わせて実施されるのが一般的です。特に上場企業など法令などで会計監査を義務付けられている企業は、監査が終了した財務諸表を株主総会に報告する義務があり、報告に間に合わない場合、上場廃止になることもあります。
一方で、会計監査を義務付けられていない企業は、半期や四半期決算のときなどに行われるところもあります。
会計監査の種類について
会計監査にはいくつかの種類があり、企業の状況や目的に応じて適切に実施され、主に「外部監査」「内部監査」「監査役監査」の3つがあります。
以下では、これら3つの種類の会計監査について解説します。
外部監査
外部監査は、企業の財務諸表が適切かどうかを、外部の公認会計士や監査法人によって行われる会計監査です。
会社法や金融証券取引法、国や地方自治体から補助金を受けている企業や法人は外部監査の対象です。
また、法律で定められていない法人であっても、任意で外部監査を受けることが可能で、信頼性を高めることが期待できます。
内部監査
内部監査は、企業自身が設置する内部監査部門が業務の妥当性や効率性を自主的に検証する監査です。財務情報に限らず、業務プロセスや内部統制の有効性まで幅広くチェックするのが特徴です。
経営陣への報告や改善提案も担い、不正の防止や業務改善を促す役割を果たします。企業のガバナンス強化に欠かせない監査です。
監査役監査
監査役監査は、会社法に基づき選任された監査役が、取締役の職務執行を監督するものです。会社法では、監査役の職務として、取締役の職務の執行を監査することが明記されています。
また、業務および財産の状況を調査できる権限を有しており、監査役は業務監査や会計監査が実施できます。
会計監査の流れおよび具体的内容
会計監査のアウトラインについて解説しましたが、会計監査はどのような流れで進んでいくのでしょうか。会計監査の流れを、具体的な内容とあわせてここでは紹介します。
会計監査の流れ
企業が作成した財務諸表の信頼性を担保するために、会計監査は段階的に進められます。
一般的な流れは以下の通りです。
- 予備調査
- 監査計画の立案
- 実地監査(会計監査)
- 監査報告書の作成
各フェーズで確認すべきポイントが明確に定められているので、企業はあらかじめ準備を整えておく必要があります。
1)予備調査
予備調査では、監査人は公認会計士として責任が果たせるかをチェックします。監査対象である企業が監査に協力的であるのか、内部統制が監査に対応可能であるのかについて確認します。
もし内部統制が確立していない場合、監査対象企業は監査に対応できるよう構築することが必要です。
2)監査計画の立案
予備調査で得た情報をもとに、監査対象の範囲や日程、手続きの方針を定めるのが監査計画です。
リスクの高い勘定科目や業務領域を、管理組織のレベルや内部統制の整備・運用状況、取引の実体などを分析して抽出します。リスク・アプローチと呼ばれる手法で、効率的な監査が可能となります。
3)会計監査
実際に企業に赴いて行う会計監査では、会計帳簿や証憑類をもとに財務諸表の妥当性を確認します。確認内容は、売上・仕入・在庫など多岐にわたり、証憑突合や現物確認などの手続きを実施します。内部統制の運用状況も再評価され、リスクの再点検も行われ、必要に応じて経営陣や担当者へのヒアリングも実施されます。
4)監査報告書の作成
監査作業が完了すると、最終成果物として監査報告書が作成され、以下の4種類の監査意見が表明されます。
| 監査意見 | 内容 |
| 無限定適正意見 | 会計書類は正しいと判断 |
| 限定付適正意見 | 不適切事項はあるが重要部分は適正と判断 |
| 不適正意見 | 会計書類は正しくないと判断 |
| 意見不表明 | …十分な証拠がなく意見を表明できないと判断 |
この意見は、企業の財務諸表が適正に作成されているかを示すもので、投資家や金融機関にとって重要な判断材料になります。
会計監査の具体的な内容
会計監査では、財務諸表の信頼性を確保するために、多岐にわたる科目や処理内容がチェックされます。以下では、具体的内容について紹介します。
- 貸借対照表および損益計算書の内容確認
- 売掛金・買掛金の残高確認
- 現金・預金・借入金の残高確認
- 引当金などの確認
- 固定資産の計上や除却処理の確認
- 伝票の確認
- 固定資産の計上や除却処理の確認
- 経理処理の状態の確認
- 経理処理状態と帳簿組織・システムの確認
- 勘定科目の確認
- 実地棚卸の確認
貸借対照表および損益計算書の内容確認
貸借対照表と損益計算書は、企業の財務状況を表す基本的な書類です。監査では、これらが会計基準に準拠して正しく作成されているか、数値の整合性が取れているかを重点的に確認します。
売掛金・買掛金の残高確認
売掛や買掛金の残高を、請求書や残高証明書などと照合し、正確であるかをチェックします。売掛金として計上している中に、未回収のものはないのか、あるいは滞っている売掛債権を適切に処理しているかどうかに関しても確認します。
現金・預金・借入金の残高確認
銀行残高証明書や通帳を精査し、帳簿との一致を確認します。特に現金については、実際に確認されることもあり、現金過不足や不正流用の有無も精査します。
引当金などの確認
将来の支出に備えて計上される引当金(貸倒引当金、退職給付引当金など)が、適切に見積もられ、計上されているかをチェックします。
過去の実績や合理的な計算根拠に基づいて計上されているかを精査します。
固定資産の計上や除却処理の確認
固定資産は長期にわたって使用される重要な資産であり、計上額や耐用年数、減価償却方法が会計基準に準拠しているかを確認します。
また、除却や売却が発生した場合は、その処理が正しく反映されているかも確認対象です。資産の実在性を証明するため、現物の有無も確認されることがあります。
伝票の確認
伝票は日々の取引を記録する根拠となるため、監査では証憑類(請求書や領収書など)と照合して、取引の正当性や記帳ミスの有無を確認します。不適切な会計処理や二重記帳、または架空取引の有無を見極めるために、伝票の内容・承認印・日付などもチェックされます。
経理処理の状態の確認
日々の経理業務が適切に行われているかは、企業全体の財務の信頼性を左右します。監査では、記帳のタイミング、内容の正確性、内部統制の運用状況などが確認されます。不備や属人的な処理がないか、標準化されているかどうかも重要な評価ポイントです。
経理処理状態や帳簿組織およびシステムの確認
会計ソフトやERPなど、企業が導入している会計システムも監査の対象となります。
システム上の権限設定や改ざん防止措置、バックアップの有無などをチェックし、帳簿記録の信頼性と継続性を確認します。
勘定科目の確認
勘定科目の選定・運用が適切であるかどうかも監査で確認されます。たとえば、雑費や仮払金など、曖昧に処理されがちな科目に不適切な取引が含まれていないかなどです。経理部門の判断基準が一貫しているかどうかもあわせて確認され、科目運用の透明性が求められます。
実地棚卸の確認
棚卸資産の実在性を確認するため、監査人が立ち会う実地棚卸が実施されることもあります。倉庫や店舗に保管されている在庫を直接確認し、帳簿残高との照合を行います。棚卸の不備や数量の誤差、不良在庫の計上漏れがないかをチェックし、資産評価の妥当性に直結する重要な手続きです。
会計監査を受ける際の注意点
会計監査を受ける際には、企業として事前に注意すべきポイントがいくつかあります。特に重要なのは、以下の3点です。順を追って確認しておきましょう。
- 資料内容の把握
- 最新の資料であるかを確認
- 監査スケジュールの管理
資料内容の把握
提出する資料の内容について、経理担当者や責任者がしっかりと把握していることが前提です。会計の監査時には、帳簿の根拠資料や会計処理の判断理由などについて質問されます。詳細に至るまで理解していなければ、監査中の質疑応答で信頼を損ねるリスクがあるかもしれません。
事前に資料の中身を確認し、説明できる体制を整えることで、監査対応の精度が高まります。
最新の資料であるかを確認
期中に固定資産の購入や除却が発生した場合、固定資産台帳の確認を行い、最新のものにしておくことが必要です。
監査スケジュールの管理
会計監査にはスケジュール管理が欠かせません。監査人との打ち合わせや資料提出の期限、実地監査の日程などを把握し、社内でも共有しておく必要があります。特に繁忙期と重なる場合は、スケジュールの余裕を持って準備することが望まれます。
遅延が発生すると、全体の進行に影響するため注意が必要です。
まとめ
会計監査は、企業の財務情報の信頼性を高め、健全な経営体制を築くうえで欠かせない重要なプロセスです。
法的義務の有無にかかわらず、外部監査・内部監査・監査役監査といった種類を理解し、それぞれに応じた適切な対応が必要です。
監査の流れや確認される項目を事前に把握し、必要な資料を最新の状態で準備することで、監査対応の精度と効率が向上します。また、監査で確認される会計処理や帳簿の整備を日常的に徹底することが、監査報告書における高い評価につながり、金融機関や取引先などステークホルダーからの信頼獲得につながります。
会計監査は単なる制度的な義務ではなく、企業の透明性と成長を支える重要な経営資源と捉えるべきでしょう。