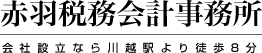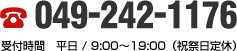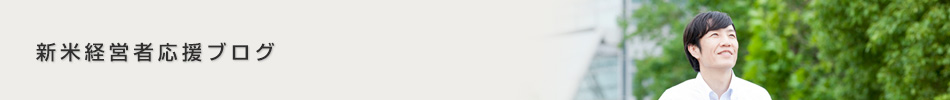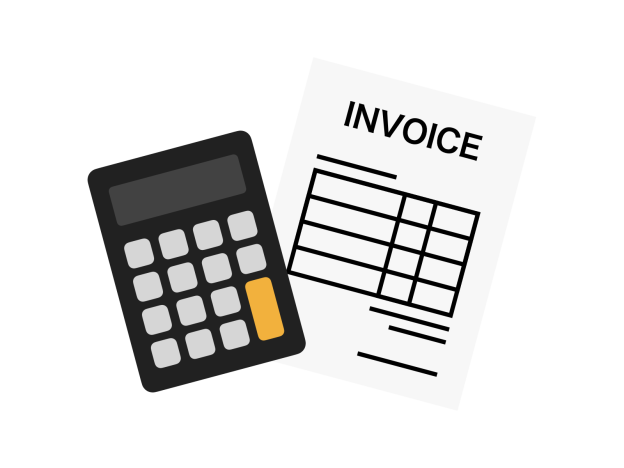
会社を設立する際、必ず登録免許税を納めなければなりません。株式会社や合同会社など形態によって算出方法が異なり、初期費用として大きな負担となることもあります。
ただし、自治体が実施する特定創業支援等事業を活用すれば、登録免許税額を半額に軽減できるなどといった利点があります。
本記事では、会社設立に欠かせない登録免許税について解説します。株式会社や合同会社といった形態ごとの計算方法、登録免許税額を半額にできる支援制度の活用法、さらに納付の具体的な手順や注意点まで幅広く取り上げます。
会社設立時は資金繰りに頭を悩ませる場面も多いため、少しでも初期費用を抑えたいと考える起業家の方も多いかもしれません。本記事を参考にスムーズなスタートアップを図ってください。
会社設立に必要な登録免許税とは
会社を設立する場合、法人登記をしなければなりません。法人登記の際に必要な費用として登録免許税があります。ここでは、登録免許税について解説するとともに、会社設立にかかる登録免許税の算出方法について形態ごとに紹介します。
登録免許税は会社を設立する際にかかる国税
登録免許税とは、登記・登録・特許・免許・許可・認可・認定・指定および技能証明について課する国税です。
会社を設立する際には、法人登記に伴い必ず登録免許税が課されます。さらに、設立時に限らず、役員の変更や本店の移転といった登記事項の変更があるたびに、その都度登録免許税が発生する点にも注意が必要です。
登録免許税は会社設立以外にも、不動産の登記や船舶・航空機登録等を行う際にも必要です。
会社設立にかかる登録免許税の算出方法
会社設立にかかる登録免許税は、以下のいずれか高い方で算出されます。
|
登録免許税は、会社形態と資本金の大小によって納付額が変動する仕組みになっています。
以下では、株式会社と合同会社それぞれの具体例を確認します。
株式会社の場合
株式会社設立時の登録免許税は「資本金 × 0.7%」で算出します。また、株式会社設立時の登録免許税最低額は15万円と決められており、計算式で得られた数値が15万円を超えた場合はその金額、15万円以下であれば15万円となります。
例えば資本金が1,000万円の場合、計算式では1,000万円×0.7%=7万円です。この場合、登録免許税最低額が15万円であるため、実際に納める登録免許税は15万円となります。
一方、資本金が3,000万円の場合、3,000万円×0.7%=21万円であり、登録免許税最低額の15万円を上回ります。そのため、納付する登録免許税額は21万円です。
合同会社の場合
合同会社を設立する場合の登録免許税の計算式は、株式会社同様「資本金× 0.7%」です。
しかし、登録免許税最低額は6万円となっており、合同会社は株式会社よりも低く設定されています。
例えば資本金500万円であれば、500万円×0.7%=35,000円ですが、納付する登録免許税額は、最低税額の6万円となります。
登録免許税を50%に軽減する方法
会社設立における必要経費である登録免許税ですが、特定創業支援等事業を活用することで登録免許税を50%に軽減できます。
ここでは、特定創業支援等事業について、および特定創業支援等事業で受けられるメリットおよび注意点について紹介します。
特定創業支援等事業とは
特定創業支援等事業は、産業競争力強化法に基づき、創業希望者や創業して間もない人を支援するため、国や自治体によるサポート事業です。地域の創業促進により、日本の産業競争力を高めることを目的としています。
国から認定を受けた自治体が「創業支援等事業計画」を商工会議所および民間事業者などと協力して実施します。
主な支援内容のひとつに、創業予定者や創業間もない事業者を対象としたセミナーがあります。「経営・財務・人材育成・販路開拓」といった分野を総合的に学べるプログラムが用意されており、事業運営に必要な知識を体系的に身につけられる点が特徴です。
受講条件は自治体によって異なりますが、1か月以上継続し、4回以上参加することが一般的とされています。
修了後は、受講した自治体より「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が交付されます。
特定創業支援等事業で受けられるメリット
「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」を交付されることで得られるメリットとして、以下の3点があるので、それぞれ解説します。
- 法人登記時の登録免許税が50%になる
- 6ヶ月前から創業関連保証の対象となる
- 新規開業資金の優遇措置が受けられる
法人登記時の登録免許税が半額になる
特定創業支援等事業で受けられる最大のメリットは、法人設立時の登録免許税が半額になる点です。登録免許税額は資本金の0.35%となります。株式会社の場合、7万5,000円に満たない場合は75,000円、合同会社の場合、3万円に満たない場合では3万円となります。
6ヶ月前から創業関連保証の対象となる
6ヶ月前から創業関連保証の対象となる点も、証明書の交付により得られるメリットとしてあります。
信用保証協会が取り扱っている保証の中に、創業関連保証があります。通常、2ヶ月以内に法人を設立し、事業を開始する具体的計画がある個人に向けての保証です。しかし、証明書があれば、6ヶ月前から創業関連保証の対象となります。
起業準備の早い段階から保証が活用でき、創業時において、ゆとりのある資金繰りが見込まれるでしょう。なお、創業関連保証の利用を検討する場合、所轄の信用保証協会あるいは取引金融機関に問い合わせてください。
条件次第で新規開業資金の優遇措置が受けられる
条件に該当すれば、日本政策金融公庫が取り扱っている「新規開業資金」における特別利率の対象になる点もメリットとしてあります。
特定創業支援等事業の注意点
一方で、特定創業支援等事業を受けることに際しての注意点として、以下の点があります。
- セミナー等の受講が必要
- 交付まで時間がかかる
セミナー等の受講が必要
特定創業支援等事業の適用条件として、自治体が主催するセミナー等を受ける必要があります。通常1ヶ月近くかかるので、起業前で忙しい事業者にとっては研修を受ける時間を確保する必要があります。
交付まで時間がかかる
セミナー受講後、登録免許税軽減に必要な「特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書」が交付されるまで、さらに時間がかかります。特に、法人設立日を決めている起業家は、事前に受講予定の自治体に交付されるまでの日数等を確認し、時間的に余裕のあるスケジュールを組むことが重要といえそうです。
登録免許税の納付方法
登録免許税を納付する場合、登記申請と同時に納付することが必要です。
登録免許税の納付方法は、以下の方法のいずれかで行います。
- 現金で納付
- 収入印紙で納付
- ATM・インターネットバンキングで納付
- クレジットカードで納付
それぞれ順を追って紹介します。
現金で納付
登録免許税は法務局の窓口で現金納付することが可能です。納付後には領収書が交付され、領収書を「登録免許税納付用台紙」に貼り付け、提出します。
手渡しで確実な反面、平日の開庁時間内に出向かなければなりません。また、登録免許税が高額な場合、大きな金額を持参するリスクも伴うので注意が必要です。
収入印紙で納付
収入印紙を使っても、登録免許税を納付することもできます。事前に郵便局や法務局で必要な金額の収入印紙を購入し、登記申請書の所定欄に貼付して提出すれば納付完了です。
なお、収入印紙の購入は現金のみとなる点に注意しましょう。
ATM・インターネットバンキングで納付
金融機関のATMやインターネットバンキングによる納付も登録免許税の納付が可能です。特にオンラインで法人登記を行った場合、法務局窓口に出向くことが不要なので便利です。
インターネットバンキングを利用する場合、金融機関との手続きが完了していることが前提となります。またATMから納付する場合は、「Pay-easy(ペイジー)」のマークがあるATMでないと対応できない点に注意しましょう。
クレジットカードで納付
近年まで、クレジットカードでの納付ができませんでしたが、2024年1月からクレジットカードでの納付が可能となりました。24時間手続きできるため、利便性を重視する起業家には有効な手段といえます。
ただしクレジットカードでの納付が可能なのは、電子申請で法人設立した場合のみです。法務局に出向いて法人設立の申請を行う場合、クレジットカードでの納付ができないので注意しましょう。
登録免許税納付における注意点
登録免許税の納付には、方法によっては注意すべき点があります。また、納付自体を怠ればどのような影響があるのかにもあわせて紹介します。
収入印紙で納付する場合
収入印紙で納付する際の注意点として、額面を誤って購入すると払い戻しができない点があります。
また、収入印紙の消印は法務局が行う点にも注意しましょう。万が一消印を行った場合、無効となり、再購入の必要があります。
クレジットカードで納付する場合
クレジットカード納付する場合、納付額の2.2%の手数料が別途かかる点に注意が必要です。例えば、15万円の登録免許税をクレジットカードで納付する場合、実際の支払いは15万3,300円になります。
また、不正防止の観点から、「3Dセキュア」登録済みのクレジットカードしか利用できません。3Dセキュアとは、オンラインショッピングの際にクレジットカードの不正使用を防止するセキュリティ機能です。
3Dセキュアへの登録方法は、カード会社により異なるので、あらかじめ確認しておくことが必要です。
登録免許税を納付しない場合
登録免許税を納付しないまま登記を申請しても、手続きは受理されません。会社設立登記であれば法人格が発生せず、事業を開始できないだけでなく、契約締結や銀行口座開設も行えません。
納付漏れは、期限に遅れる程度の問題ではなく、登記そのものが成立しない重大なリスクを伴うので、申請と同時に必ず納付を完了させるようにしましょう。
まとめ
登録免許税は、法人形態によって最低納付額が異なるものの、必要不可欠な初期費用です。
特定創業支援等事業を活用することで、登録免許税額を半分にできるといった利点があります。初期投資を抑えたい起業家にとっては、検討してみる価値があるといえるでしょう。
登録免許税の納付方法には、現金・収入印紙・インターネットバンキング・クレジットカードなど複数の選択肢があります。起業家は状況に応じて適した方法を選べますが、それぞれに特徴や注意点があるため、事前に把握しておくことが大切です。
登録免許税はスタートアップには必要不可欠な費用です。しっかり理解して、スムーズな会社設立を行いましょう。