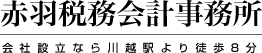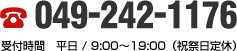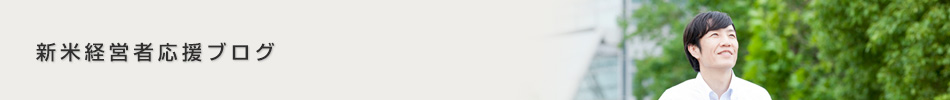企業経営において、資金繰りが厳しいという状況は、売上や利益の数字だけでは判断できません。
黒字であっても、資金不足に陥ることがあります。資金繰りが厳しくなる要因は、収益構造の歪みや管理体制の不備などさまざまです。
特に、利益の出ない仕事を続けたり、計画性なく新規事業に挑戦したりすれば、手元資金は確実に減少します。また、経営者が資金の流れを理解していないと、気づかない間に資金ショートを招く恐れがあるかもしれません。
本記事では、資金繰りが厳しくなる原因や資金繰りが厳しくなる企業の特徴について解説します。あわせて、キャッシュフローを見直すべきポイント、および絶対に避けるべき行動について紹介しますので、資金繰りに悩まれている経営者の方は参考にしてください。
会社の資金繰りが厳しくなる要因
会社の資金繰りが厳しくなる背景には、収益構造や経営判断の誤りといった根本的な問題があります。これらの問題を経営者が理解しておかなければ、資金繰りが厳しくなるので注意が必要です。
以下では、会社の資金繰りが厳しくなる要因について紹介します。
収益よりも損失が大きい
企業が収益を上げていても、費用や損失がそれを上回ると資金繰りは一気に脆弱になります。
例えば、家賃・人件費・固定費が高止まりしたまま売上が減少したり、予期せぬ損害が出たりすると、黒字決算であっても手元資金が枯渇し「黒字倒産」のリスクが高まります。
実務では、帳簿上の利益と現金収支がズレているケースが多く、利益イコールキャッシュと捉えてしまうと資金繰り悪化に気付かず手遅れになりかねません。
利益が出ない仕事を受ける
売上を追うあまり、利益率の低い仕事を受注し続けると、売上高は増えても手元に残る現金が少ないという悪循環に陥ります。
特に、人件費・材料費・仕入代金の負担が大きい一方で、納期・支払条件・追加コストなどを見切れず受けてしまうと、収益以上にコストがかさみます。
結果として、忙しくても手元資金が増えず、支払いのための資金がひっ迫する場面が出るかもしれません。
計画を立てずに新規事業に挑戦する
新規事業は成長の源となる一方で、準備不足や資金計画の甘さが資金繰りを圧迫する原因ともなります。
売上実現を見込んで設備投資・人員投下・仕入先契約を先行させた結果、入金の見込みが立たないうちに支出が先行する状況が生まれやすくなります。
さらに、既存事業との資金の兼ね合いや回収サイト、支出タイミングのズレを考慮せずに動くと、短期間で資金ショートの危険が高いです。
経営者が理解していない
資金繰りのキモである現金の増減や支払い・入金のタイミング、および手元資金の残高について、経営者自身が理解・関与していない場合、異変に気づきにくくなります。
経理部門任せ・帳簿上の利益のみを重視する姿勢では、資金の流れに歪みがあっても対策が遅れがちです。
経営者が財務・会計に関する知識が乏しいと、資金繰りの警報を見逃してしまうケースが発生する恐れがあります。
資金繰りが厳しい企業の特徴
資金繰りが厳しい企業には、いくつかの共通した傾向があります。以下では、資金繰りの悪化を招く典型的な特徴を整理します。
- 慢性的な赤字体質
- 売掛金の回収が遅れている
- 資金繰り計画を立てていない
- 売上の急拡大により資金繰りが追いついていない
- 過剰在庫・不良在庫の増加
慢性的な赤字体質
売上があっても、固定費や原価がそれを上回ってしまうことが慢性的に続くと、会社の資金繰りは極めて厳しいものになります。
特に人件費・家賃などの固定費が高いうえに、価格設定が甘く利益率が出ていないと、赤字体質から抜け出せません。
実際、赤字体質の企業は「売上はあるが利益は出ない」「経費を切れずに延々と赤字」という傾向があります。こうした状況下では、利益が出ていないにもかかわらず借入金返済など負担が重なり、資金ショートに陥るリスクが高まります。
売掛金の回収が遅れている
売上として計上はされていても、実際の入金が遅れていると、手元資金が枯渇しかねません。
取引先の支払いが遅れたり、請求書発行が遅れていたり、決済サイトが長期化して入金が見込めないと、コストや仕入代金の支払いが先に立ち資金が止まってしまいます。
売掛債権の未回収や回収の遅延は、資金繰りを圧迫する典型的な原因です。
取引先の信用状態や自社の請求管理の遅延が背景にあることも多く、経営判断の遅れにつながる恐れがあります。
資金繰り計画を立てていない
資金繰りの計画を立てずに事業運営していると、入金と支出のタイミングの乖離に耐えられず、気がつけば資金ショートに陥ってしまいます。
損益計算書上は黒字であっても、キャッシュの流れが追えていなければ意味がありません。
特に、入金より支出が先であるという流れを把握していないと、黒字なのに資金がない状態が起きます。資金繰り計画を立てて数か月先の入出金を可視化することが、危機回避には不可欠です。
売上の急拡大により資金繰りが追いついていない
売上が拡大していると一見好調ですが、実は資金繰りにおいては先行きの厳しさが内在しています。
売上増に伴い、仕入資金や人件費なども比例して支出が増加します。手持ち資金に余裕がないと、手元資金が枯渇しかねません。
売上の急激な上昇は、忙しいのに資金が足りなくなる事態が生まれやすくなり、資金繰りが厳しくなってしまいます。
過剰在庫・不良在庫の増加
在庫が多いと安心と考えることがありますが、売れ残った在庫は資金が「商品」へと固定化され、自由に使える現金が減ります。
中小企業では、保管コストや倉庫費用、管理人件費も重荷となるため、、在庫を抱えすぎるとキャッシュフローを停滞させる要因となります。
適正在庫の維持、棚卸の見直し、回転率の改善が資金繰り改善には欠かせません。
資金繰りの厳しい企業が見直すポイント
さまざまな理由で、資金繰りが厳しくなるのですが、経営者は会社のどのような点を見直せばいいのでしょうか。主に、以下の4点が見直す点としてあります。
- 在庫を減らす
- 遊休資産の売却
- 資金繰り表の作成
- 金融機関に相談する
それぞれ順を追って解説します。
在庫を減らす
本来、在庫は商品として売上につながり、売上代金を回収して資金が循環します。
在庫を抱えすぎることは、売上につながっていないため、資金繰りが悪化します。
スムーズな資金繰りを目指すには、過剰在庫を避けなければなりません。それには、適正な在庫はどれくらいであるのかを把握しなければなりません。
売れ筋や滞留品、倉庫保管や管理コストも含めた在庫に関する特性を認識することで、回転率を上げることでき、厳しい資金繰りの厳しい企業が取り組むべきポイントといえるでしょう。
遊休資産の売却
自社に本業に使われていない土地や建物などの遊休資産は、維持管理コストが必要なため、自社の資金繰りを圧迫します。
遊休資産を売却して現金化することにより、資金繰りの改善が可能です。また、売却による収入だけでなく、固定費や維持費、税負担も軽減できます。
売却を検討する際には、資産の担保設定や売却時期、税務における影響も視野に入れて検討することが重要です。
資金繰り表の作成
資金繰り表は、自社の毎月の収入や支出が可視化できるもので、手許現金の過不足が予測できます。売上入金や仕入資金・人件費等のタイミングが事前に把握できるため、資金ショートに陥ることが避けられます。あわせて、入金の遅延や支払いのピークおよび資金不足のタイミングが事前に予測できるので、経営判断の質を高めることが可能です。
金融機関に相談する
資金繰りが厳しいと感じた場合、早期に金融機関に相談することで、資金繰りの悪化を食い止めることが可能です。
金融機関に相談する内容として「資金の調達」「返済の見直し(リスケジュール)」があります。
<h4>資金を調達する</h4>
運転資金や投資資金を確保する際は、銀行や信用金庫、日本政策金融公庫などの融資を検討するのが基本です。
融資には、金融機関が単独で実行する「プロパー融資」と、信用保証協会の保証を付ける「保証付融資」があります。
いずれの場合も、資金繰りが悪化した要因を整理し、今後の改善策と返済原資を具体的に示すことが必要です。
返済の見直し(リスケジュール)
既存の借入金の返済が重荷となり、運転資金を圧迫している場合には、返済条件の見直し(リスケジュール)を早めに検討することが重要です。
金融機関へ相談する際は、返済猶予期間の設定や月々の返済額の減額といった具体的な提案を示すことが求められます。
そのうえで、見直し後の資金繰り表を提示し、返済計画の実現性と事業再建への意欲を示すことで、相手の理解を得やすくなります。
資金繰りが厳しくてもやってはいけない行動
資金繰りが厳しくなった際には、つい焦りから場当たり的な対応を取りがちです。
しかし、短期的な資金確保を優先するあまり、長期的な信用や経営基盤を損なう行動を取ってしまうと、状況はさらに悪化します。
- 街金融や商工ローンからの資金調達
- 税金や社会保険料の延滞
- 融通手形の振り出し
- 交渉なしでの支払先への遅延
これらはいずれも一時的な資金難の解決には見えても、企業の信頼・再建可能性を大きく損なう行動です。以下で、それぞれのリスクと注意点について詳しく解説します。
街金融や商工ローンからの資金調達
資金繰りが厳しい時、借りられるところから安易に資金調達しようとすると、後々さらに深刻な問題を招く可能性があります。
特に街金融(高金利が通常)や商工ローンなど、信用力低下時に頼りがちな融資は、返済負担が増大し、信用情報へも影響します。金融機関からの新規(追加)融資への足かせとなりかねません。
税金や社会保険料の延滞
会社の資金が厳しいため、税金や社会保険料の支払いを先送りにするのは避けなければなりません。
延滞には加算金や延滞利息が発生し、場合によっては行政処分や差押えの恐れもあります。
特に、源泉所得税や消費税は、「預り金」としての要素があるため、延滞することは、使い込みと考えられます。金融機関や取引先からの信用低下と見なされる恐れがあるので、延滞しないようにしましょう。
融通手形の振り出し
実体のない取引を装って手形を振り出し、手形割引を利用して資金を確保する「融通手形」は、資金繰りの悪化した企業が手を出す恐れのある行動です。
商取引に裏付けがないため、金融機関側も割引を拒むケースが多いため、支払期日までに決済できなければ不渡りとなります。
結果として、銀行取引停止処分となり、信用失墜となってしまうため、絶対に行ってはなりません。
交渉なしでの支払先への遅延
支払先への支払いを断りもなく遅延させることは、企業の信頼を一気に失うこととなります。また一度失った信頼を取り戻すことは、容易ではありません。
長い取引があり、信頼関係が築かれている取引先であれば、事前に相談することで、支払いをずらせてもらえるかもしれません。しかし、断りもなく支払いを遅延すると、今後の取引だけでなく、他の取引先にも波及する恐れがあるので決して絶対に行ってはいけません。
まとめ
資金繰りが厳しくなる背景には、赤字体質や売掛債権の回収遅延、無計画な投資など、経営の根本にかかわる問題が潜んでいます。
キャッシュフローを改善するためには、適正な在庫管理や遊休資産の現金化、資金繰り表による可視化、金融機関への相談などを行うことが必要です。
ただし、資金繰りが厳しいからといって、街金融などから資金を調達したり、税金や社会保険料を遅延したりすることは避けなければなりません。自社の信用力の低下につながるからです。
資金繰りが厳しくなると、たとえ黒字であっても資金ショートを引き起こし、倒産する恐れがあります。入金や出金のタイミングを正確に把握することで、厳しい資金繰りからの緩和が期待できるでしょう。